院内検査

体調が悪い、怪我をしたなど、何か病気にかかった場合にまずはお話を伺い、体をチェックし、検査を行います。
動物と人とで一番異なるのは、動物は「ここが痛い」とか「吐き気がする」とかを話すことはありません。症状を見て、触って、検査して確認しないといけません。
そのため、人よりも検査がより多く必要になることがあります。
当院では様々な検査機器、手術機器を揃えており、一般的な病気であれば検査から治療まで行うことが可能です。
血液検査
何か体調が悪いとき、まずは血液検査を行います。
血液検査では、
- 貧血の有無
- 炎症像の有無
- 肝臓や腎臓の評価
- 栄養状態
- 塩分バランス
などを確認します。
これらはスクリーニング検査といい、これだけですべての病気を特定できるわけではなく、疑われたものに対して、精査が必要になります。

カタリストOne
一般的な血液化学検査から内分泌検査、尿検査まで1台で幅広い検査に対応しています。
通常の血液検査はもちろん、SDMA(早期腎臓病の発見)、T4(甲状腺ホルモン)、FRU(糖尿病がうまく管理できているか)、UPC(尿に蛋白が出ていないか)など、腎臓病や糖尿病などの慢性疾患の早期発見、安全な管理に役立つ機能も充実しています。
干渉物質を最小限に抑制するよう動物専用に開発された検査スライドを採用しています。
プロサイトDx
当院では先進的な「レーザーの目」で血液をより正確に分析できる、どうぶつ専用の自動血球計算装置を導入しています。
- 貧血の有無やタイプを調べる網赤血球数の正確なカウント
- 体の中の状態をより正確に調べる白血球5分類
- 出血性疾患などを調べる(犬・猫)血小板数の正確なカウント

血液検査では内分泌を検査することも可能です。高齢になってきてなんとなく元気がないとか、猫ちゃんですごく元気なのに痩せてきたときなどは甲状腺ホルモンの検査を推奨いたします。
また、よく水を飲んで排尿をするとか、皮膚の状態がなかなか良くならないなどの場合はコルチゾールの検査を推奨いたします。

レントゲン検査
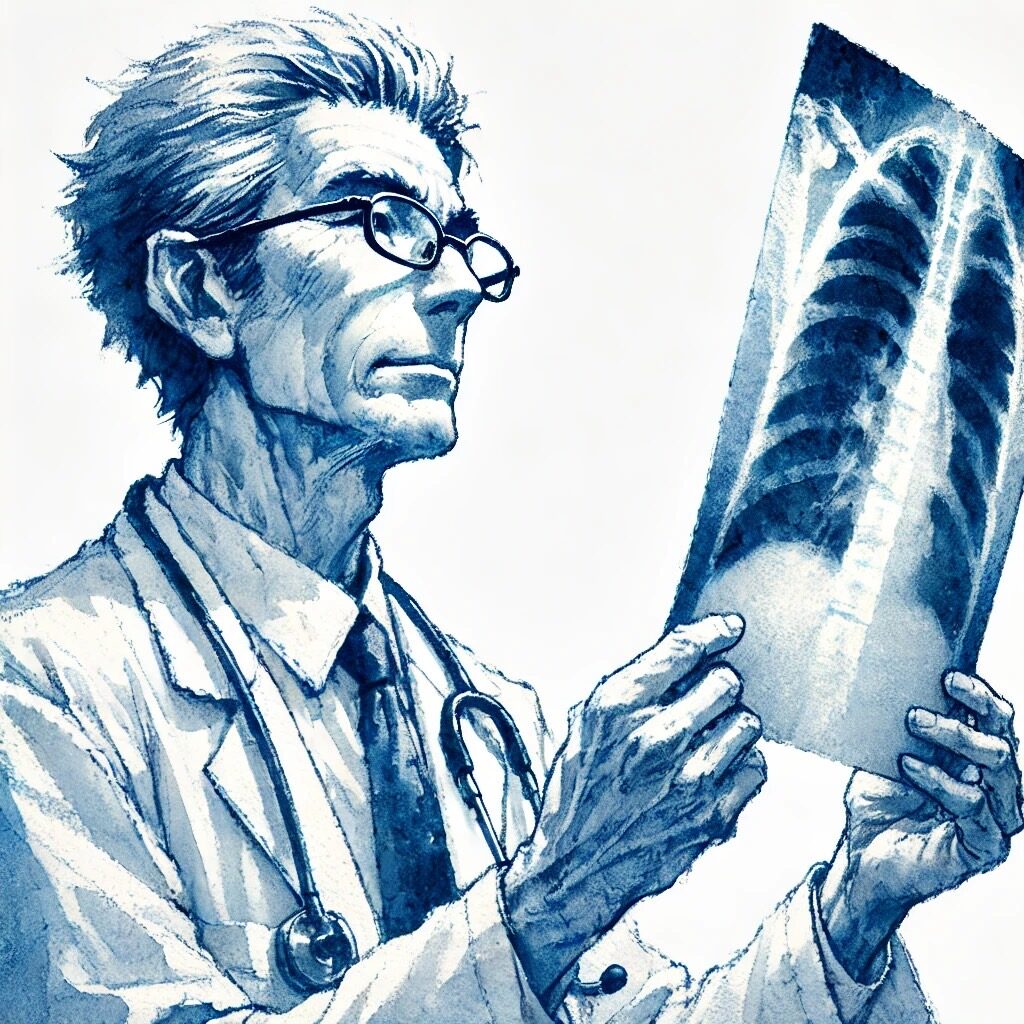
レントゲン検査では内臓の大きさや形、何か正常と異ならないか、足などを痛がっている場合は骨や軟部組織に異常はないかなどを検査します。
また、異物を食べてしまったときもレントゲン撮影を行ったり、造影を行って閉塞がないかを検査します。ビニールなどはレントゲンではうつらないため、通過障害がないかどうかを調べます。
レントゲン検査もスクリーニング検査にあたり、ここで異常があった場合は精査が必要になります。
超音波検査

超音波検査はレントゲンでわからなかった内臓の内部の構造を確認するために行います。
たとえば一般身体検査やレントゲンで心臓が悪そうだなと診断した場合は、その心臓の動きや状態を超音波検査で確認し、どの薬を選択するかを考えます。
また、血液検査で腎臓の数値が悪かった場合は、腎臓の形はどうか、結石などはないかなどを調べることが可能です。
ピンポイントで検査することが多いため、レントゲンと組み合わせて検査することが一般的です。
顕微鏡検査
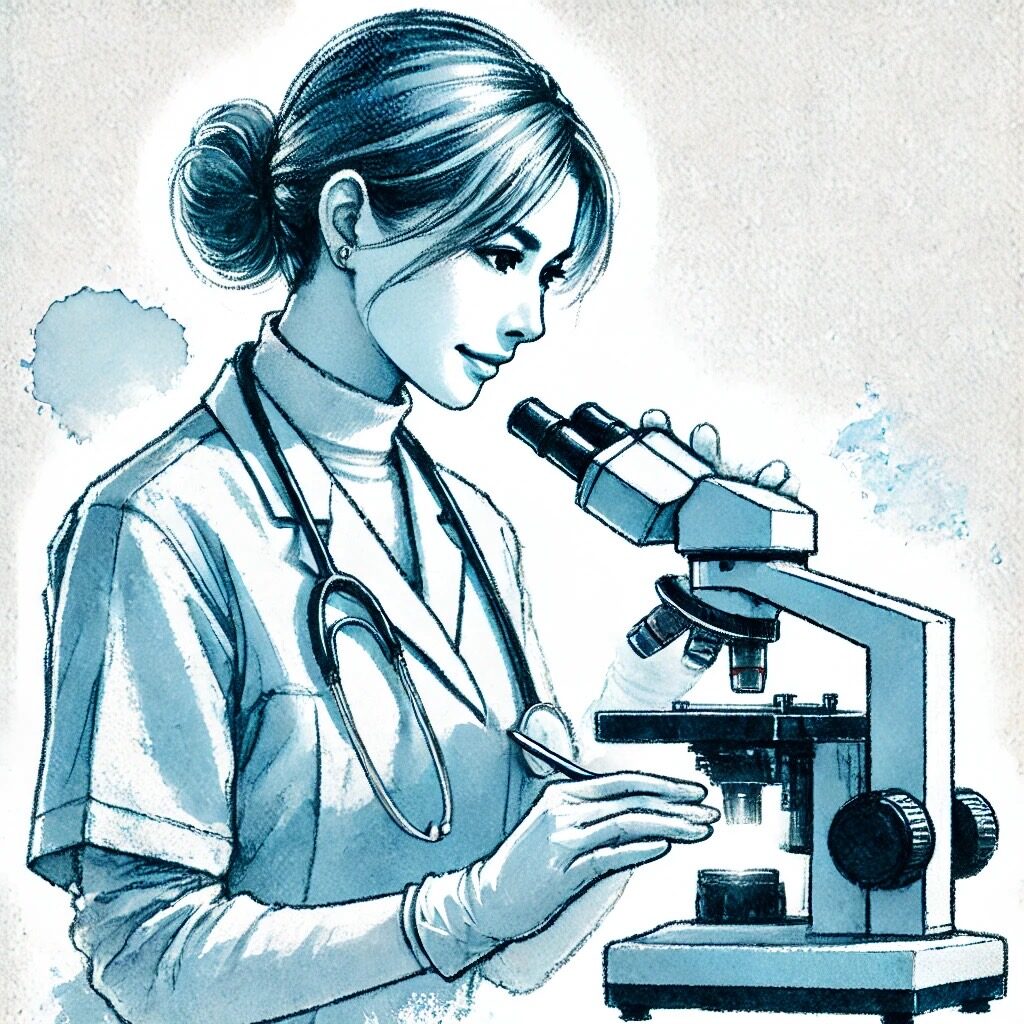
顕微鏡は裸眼では見えないものを確認するための検査機器で、一般的には、
・便の検査で寄生虫や菌の状態の確認
・皮膚の検査で菌やカビ、寄生虫の確認
・血液の検査で寄生虫や貧血の鑑別
・腫瘍などの細胞を採取して、検査
・尿を採取して、結晶や細菌の有無の確認
などを検査します。
